マーケティングオートメーション(MA)とは、顧客のニーズを捉え、そのためのマーケティング活動を自動化することで効率性を高めながら顧客に商品を販売することを可能にするツールです。本記事では、「マーケティングオートメーション(MA)の概要」をはじめ「SFAやCRMとの違い」「導入における検討ポイントや流れ」などについて解説します。
1. マーケティングオートメーション(MA)とは?
マーケティングオートメーション(MA)とは、ITツールを活用することで、顧客情報の収集や蓄積、見込み顧客の育成、販売促進活動やその結果の分析、といった企業におけるマーケティング活動を「自動化させる仕組み」のことです。
マーケティングオートメーション(MA)の仕組みを社内に構築することによって、これまで人的工数を要していたマーケティング業務の自動化が可能になり、マーケティング活動の効率化や業務の生産性向上を期待することができます。このような効率化や生産性向上の実現を目指して、大企業だけでなく、中小/中堅企業においてもマーケティングオートメーション(MA)の仕組みを導入しようとする動きが近年活発化しています。

1-1. マーケティングオートメーション(MA)でできること
マーケティングオートメーション(MA)を活用することで、以下のことを実現できます。
・リードの獲得を効率化し、多くの商談をより短時間で実施
・カスタマージャーニーを視覚的に管理
・興味関心の高いユーザーがwebページに訪問した時のみ、特別なポップアップを表示
・ユーザーの興味関心にパーソナライズ化されたメルマガ配信
このようにマーケティングオートメーション(MA)を活用することで、工数を削減しながらより効果的なマーケティング施策を実施することが可能になります。
1-2. MAとSFA、CRMとの関係
ここではマーケティングオートメーション(MA)とセールス・フォース・オートメーション(SFA)/カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)の関係性について解説していきます。
まずマーケティングオートメーション(MA)は、見込み顧客(リード)の獲得/育成/選別を行います。 マーケティングオートメーション(MA)で獲得した受注可能性の高い見込み顧客(リード)を営業部門に受け渡し、セールス・フォース・オートメーション(SFA)で案件や商談等の管理を効率的に行い、受注へつなげていきます。 受注後はカスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)で顧客データを管理/活用し、顧客との関係性を維持/向上させながらサービス利用のサポートや、アップセル/クロスセルにつなげていくのがマーケティングや営業活動の一連の流れです。

マーケティングオートメーション(MA)とセールス・フォース・オートメーション(SFA)/カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)は独立して機能するツールですが、各ツールを連携することが可能です。そのためにはツールやソフトウェア、プログラム、webサービス同士を連携させるAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)などの利用が必要です。
連携することで、マーケティングオートメーション(MA)で獲得した顧客を自動的にSFA/CRMへ連携できるため、より効率的にマーケティングからセールス、顧客管理を運用できます。

上記で述べてきたマーケティングオートメーション(MA)とCRM、SFAのそれぞれの違いに関して、下記資料にてより詳しく説明をしておりますので是非合わせてご一読ください。
2. マーケティングオートメーション(MA)の主な機能
先述した通り、マーケティングオートメーション(MA)は見込み顧客の(リード)の獲得/育成/選別を行うことができ、この一連のプロセスをデマンドジェネレーションと呼びます。①リードジェネレーション(獲得)、②リードナーチャリング(育成)、③リードクオリフィケーション(選別)の3つのプロセスを経て、見込み顧客の受注確度を高めていく手法です。デマンドジェネレーションは、主にBtoBのマーケティングにおいて活用されています。

2-1. リードジェネレーションによる顧客の獲得
リードジェネレーションとは見込み顧客(リード)を獲得するための機能です。デジタル広告やSEO、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア活用などの施策でwebサイトへ誘導したユーザーに対して、個人情報を開示してもらうようアプローチすることでリードを獲得します。具体的な機能としては以下の5つが挙げられます。
1. ポップアップ
2. リコメンド
3. プッシュ通知
4. ランディングページ/フォーム設置
5. リターゲティング広告
2-2. リードナーチャリングによる顧客の育成
リードナーチャリングは、獲得したリードに対して、メールや電話、ポップアップなどのレコメンド機能やプッシュ通知、リターゲティング広告等を活用して購買意欲を高めていく活動です。顧客の属性や嗜好、興味の度合い等の情報を把握しておくことで、リードナーチャリングをより効果的に実施することができます。 また、マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用することでこのような情報を統合的に管理でき、最適なタイミングで最適な施策を実施することが可能となります。
[詳しくはこちら]
・リードナーチャリングとは?手法や事例、サービスを紹介
2-3. リードクオリフィケーションによる顧客の絞り込み
リードクオリフィケーションは、多くのリードの中から受注可能性の高いリード(ホットリード)を抽出し、営業部門が効率的に受注するためのリストを作成する活動です。 マーケティングオートメーション(MA)ツールには、リードの属性や行動履歴等をもとに受注可能性を測定するためのスコアリングという機能が搭載されています。 また、抽出したホットリードリストを効率良く連携する、SFA連携機能が搭載されているツールもあります。
マーケティングオートメーション(MA)ツールを体験してみる!
※b→dashのマーケティングオートメーション(MA)ツールのUI/UXを体験出来ます!
3.マーケティングオートメーション(MA)の効果は?
マーケティングオートメーション(MA)導入によって、改善することができる指標の一例は以下の通りです。
3-1. メール開封率
マーケティングオートメーション(MA)ツールの機能の中には、「メールマーケティング」があります。これはメールにより新規顧客の獲得や育成を行うために使用する機能です。
そしてこの機能を使う上で、「メールが開封されているかどうか」は重要な指標になります。せっかく送信したにもかかわらず、見られずに破棄されてしまっては意味のないものになってしまうからです。
マーケティングオートメーション(MA)ツールを使うことによって、開封率を可視化し、どのような顧客が開封に至っていないか、どのような内容だと開封してくれるかなどを把握することができます。それにより、開封に繋がっていない部分を改善していくためのPDCAを回すことができるのです。
また、件名のABテストなどを行うことでさらに詳細な改善点を見つけることができます。
[参考記事]
・メルマガって?メルマガ(メールマガジン)の基礎知識から配信方法、成果を上げるコツまで徹底解説
3-2. CTR
開封率を改善し、開封されたとしても、メール文に記載されているURLや広告のクリック率(CTR)が悪ければ、成果に繋げることはできません。メールが開封されているかどうかに加え、文中の広告やURLがクリックされているかを測定することで、メルマガの件名や内容を改善につなげることができます。
これもマーケティングオートメーション(MA)ツールを導入することで、クリック率を可視化することができ、適切な改善を繰り返すことができます。
3-3. 受注率
マーケティングオートメーション(MA)を導入することで受注率の改善にもつなげることができます。
その理由は、データに基づいて効率的なアプローチをすることができるためです。
例えば、
マーケティングオートメーション(MA)ツールを使用することで、顧客を確度の高いリードへと育成することができ、結果的に受注率が上がることになるのです。
[MA活用事例一覧]
・【導入事例:株式会社アスカネット様】
・【導入事例:穴吹カレッジグループ様】
・【導入事例:ブランシェス株式会社様】
・【導入事例:株式会社ダスキン様】
4. マーケティングオートメーション(MA)の市場規模
MAの国内市場規模は2014年に米国Oracle社が日本でMAツールのサービス提供開始して以来、拡大し続けています。DMP/MAの市場規模は、2020年に543億円だったものの、2026年には865億円[注1]まで成長すると予測されています。

[出典]
株式会社矢野経済研究所「DMP/MA市場に関する調査(2021年)」(2021年11月10日発表)より当社作成
その理由の一つが、マーケティングに対する意識が高まっていることです。近年、インターネットの普及により、あらゆる情報をオンラインで入手できるようになりました。
消費者庁の調査によると、BtoCでは85.8%[注2]の消費者が、買い物をする前にインターネットで情報収集をしています。
また、webマーケティング企業の調査によると、BtoB企業の56.6%[注3]が製品やサービスを購入/契約する前にインターネットで情報収集しており、インターネットサイトの閲覧後は57.9%[注3]が企業の資料をダウンロードしています。このように昨今消費者は、必要な情報を事前にオンラインで収集したうえで、製品やサービス提供企業へコンタクトする傾向にあります。

[出典]
株式会社矢野経済研究所「DMP/MA市場に関する調査(2021年)」(2021年11月10日発表)及び
消費者庁「令和5年版消費者白書」より当社作成
そのため、営業担当者が導入検討段階のリードに会うこと自体が近年難しくなっており、ようやくリードにコンタクトできた時にはほぼ選定が終わってしまっている、といった状況が多く発生しています。つまり、企業側からすると「会えない」「ニーズがわからない」「競合の情報も持ち併せている」リードにマーケティングを活用して非対面で効果的にアプローチし、成約まで繋げて行けるかが重要視されています。そのような中で、「非対面での顧客開拓を仕組化」を実現できるマーケティングオートメーション(MA)が注目され、導入が進むことで市場規模も拡大しています。
[注1]
株式会社矢野経済研究所「DMP/MA市場に関する調査(2021年)」(2021年11月10日発表)
[注2]
消費者庁「令和5年版消費者白書」
[注3]
株式会社グリーゼ「BtoB製品購入プロセスにおけるWebマーケティングの重要性(2023年版)」
5. マーケティングオートメーション(MA)の目的
マーケティングオートメーション(MA)の目的は、「BtoB事業におけるマーケティングオートメーション(MA)」と「BtoC事業におけるマーケティングオートメーション(MA)」で大きく異なるため、それぞれ分けて説明いたします。
5-1. BtoB事業におけるマーケティングオートメーション(MA)の目的
BtoB事業におけるマーケティングオートメーション(MA)は主に「新規顧客の獲得」を目的としており、潜在顧客や見込み顧客に効率的にアプローチするために活用されます。具体的には、webサイトのようなオンラインチャネルや、展示会やイベントといったオフラインチャネルで獲得した潜在顧客に対して、顧客の属性情報や企業の所属業界等の情報に応じて、商品紹介パンフレットやホワイトペーパーといった案内物を出し分ける、といった活用をします。
そのため、BtoB事業用のマーケティングオートメーション(MA)ツールでは、リード管理機能、スコアリング機能、メール配信機能といった機能を有していることが多くあります。
[参考記事]
・【BtoB】マーケティングオートメーションの導入とおすすめツール
5-2. BtoC事業におけるマーケティングオートメーション(MA)の目的
BtoC事業におけるマーケティングオートメーション(MA)は、CCCM(Cross Channel Campaign Management)とも呼ばれ、主に「既存顧客の育成」を目的としており、メールやLINE、SMSといった複数の販売促進チャネルを組み合わせて、顧客にアプローチすることを指します。具体的には、例えば、ECサイトを運営する企業であれば、商品を初めて購入した顧客に対して2回目の購入を促すために、購入後1週間後にクーポンメールを配信し、そのメールを開封しない顧客にはLINEで再度クーポンメールを配信する、といった活用方法があります。
BtoC事業におけるマーケティングオートメーション(MA)ツールは、「メール」「LINE」「SMS」といった顧客にアプローチするチャネルに関する機能や、複数のチャネルを組み合わせるシナリオの機能などが存在します。
6. マーケティングオートメーション(MA)のメリット
ここからは、マーケティングオートメーション(MA)のメリットについて説明していきます。
6-1. 獲得した見込み顧客を資産化
マーケティングオートメーション(MA)は、見込み顧客情報の収集から商談化までの段階を効率的に管理し、商談数を最大化するツールです。顧客はすぐに商談に応じないことがあり、情報収集や競合比較を経て商談化するのが一般的です。MAを使えば、顧客との連絡を自動化し、商談化の可能性の高い見込み顧客を把握できます。これにより、効率化された営業活動で商談獲得数を増やし、見込み顧客を資産化することができます。
6-2. 営業が見逃していた案件/商談の獲得
マーケティングオートメーション(MA)を用いると、従来見逃され傾向にあった見込み顧客を商談に結び付けることが可能です。webやメールを通じたコミュニケーションにより、見込み顧客の状況を明確化し、受注可能性の高い顧客を特定できます。さらに、分散している見込み顧客情報を統合し、継続的なコミュニケーションを通じて、有望な見込み顧客を営業に効率的に引き渡すことが可能です。
6-3. 営業活動の効率化
営業活動の効率化を図るためには、マーケティングオートメーション(MA)の活用が重要です。従来は顧客との関係性構築に時間を費やしてきましたが、顧客情報収集の主要手段がインターネットに移行しています。商談可能性の低い見込み顧客とのコミュニケーションを自動化し、営業は商談の可能性が高い顧客に集中できます。これにより、営業活動を効率化し、同時に顧客開拓も行うことができます。
6-4. マーケティング活動を簡単に行える
マーケティング活動を簡単に行うためには、複数のツールを一つのプラットフォームに統合することが重要です。これにより、見込み顧客毎にデータが紐づき、効率的なマーケティング活動が可能になります。しかし、日本ではまだ多くの企業が複数のツールを使用しています。そのため、導入にはコストと時間の投資が必要ですが、見込み顧客毎に最適なコミュニケーションを行う重要性は高く、効率的に成果を上げるためにも必要となります。
7. マーケティングオートメーション(MA)導入時の注意点
これまで述べてきたように、大量のデータを扱うマーケティングでは、必要不可欠となっているマーケティングオートメーション(MA)ツールですが、ツールを導入したものの効果的に使うことができず、その結果メールの一斉配信しか活用できていないというケースも多いです。ここでは、マーケティングオートメーション(MA)を導入した企業で実際に起こってしまった失敗について紹介します。
失敗事例①:目的/目標が不明瞭
まず最初によくある失敗例として挙げられるものは、ただ漠然と「マーケティングオートメーション(MA)ツールを入れればうまくいく」という思い込みから、導入すること自体を目的としてしまっているうことです。
これにより、導入後の運用において、どのような目標を追ってPDCAを回すべきか、明確にできていないため、ただ導入しただけで終わってしまいます。まずマーケティングオートメーション(MA)ツールを導入する前に、目的を明確にし、導入後に達成すべき数値目標を置くことが重要です。目標については、「リード数を〇%向上」などより具体的に置くことがよいでしょう。
失敗事例②:保有リード数が少ない
マーケティングオートメーション(MA)は、前述のとおり、企業におけるマーケティング活動を「自動化させる仕組み」ことを指しています。そのため、メールマーケティングやメルマガなどの施策を始める際に。導入を検討されることも多いと思います。しかし、メールを配信しようとしても、「精査後のリード数がほとんどない」、「そもそものリード数が少ない」などの理由から、対象となるリードの母数が少なく、結局数百件しか送信することができなかったというケースは多々あります。
これでは、ツールを導入しても十分な効果を発揮することができず、多額のコストがかかってしまうだけとなってしまいます。このような事態を引き起こさないためにも、ある程度対象となるリード数は必要となります。
またもし、現在自社の保有リード数が少ないようであれば、「イベントにより見込み顧客を獲得する」「web施策によりリードを集める」など、リード保有数を増やすところから始めるのがよいでしょう。
失敗事例③:機能が複雑で使いこなせない
前提、マーケティングオートメーション(MA)ツールは、アメリカで開発されたものが最初に日本で提供されたものです。そのため、名前を聞いたことがあるツールの多くは海外製品であり、非常に高機能なツールです。これらのツールを完璧に使いこなすことができるのは、何年もマーケティングに携わり、十分なスキルが身についているベテランぐらいではないでしょうか。
これからマーケティングに取り組み始める方や、専門の知識がない方にとっては、最低限の施策で精一杯になってしまい、十分にツールを使いこなすことができていない状態に陥ることが多いです。
また、ツールベンダーによっては、それらのサポートに費用がかかることもあります。
このような状態では、十分にマーケティングオートメーション(MA)ツールを使いこなすことは難しいでしょう。
8. マーケティングオートメーション(MA)導入の成功事例
続いて、実際にMAを導入した企業の成功事例を、BtoCの場合とBtoBの場合に分けてそれぞれ2パターン紹介していきます。
8-1. BtoCの場合
化粧品ECのE社のケース
化粧品を自社ECサイトで販売するE社は、1回目の購入に至ったものの、2回目の購入に至らないユーザーが多いという課題を抱えていました。マーケティングオートメーション(MA)ツール導入以前は全顧客に対して同一コンテンツを一斉メール配信しておりましたが、マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入し、顧客一人ひとりに最適化したコンテンツを出し分けました。具体的には、1回目の購入商品と、過去のサイトの閲覧履歴をもとに、興味がありそうな商品カテゴリをメールでおすすめしました。結果、2回目購入率が150%増加し、LTVも115%増加させることができました。
旅館運営会社のF社のケース
長年旅館を営むF社は、団体客から個人客メインにターゲットを切り替えた際、顧客の多用化や予約管理の煩雑化といった問題に直面していました。そこで、宿泊客の傾向や行動パターンの見える化をし、マーケティングオートメーション(MA)に活用。業務の自動化とともに、キャンセル率の低下やキャンセル後のスムーズなリカバリーといった点で確かな効果がもたらされました。さらに、顧客のニーズに応じて、メールのコンテンツを出し分ける施策にも成功します。あらゆるユーザーに有益な情報が届けられることで、ポジティブな口コミや評価も同時に目立つようになりました。
8-2. BtoBの場合
人材育成サービスのG社のケース
人材育成サービスをメインに提供しているG社においては、従来の新規顧客獲得は、経営上層部からの紹介に依存していた背景があり、新たな新規顧客獲得ルートの発掘が喫緊の課題となっていました。そこでマーケティングオートメーション(MA)ツール導入時は、まず営業/マーケティング部門の責任者が、試験的にマーケティングオートメーション(MA)ツールを活用。グループウェアを通してその効果を発信するにつれ、徐々に社内全体にツールが浸透していったようです。見込み客の動向を正確に把握できるようになったため、より効果的な営業アプローチが進展します。結果的に問い合わせ数や商談数が急増し、MAツール導入前の3倍の売上を達成しました。
オフィス用品販売のH社のケース
オフィス用品の販売で有名なH社は、BtoBとしてオフィスデザインなどのファニチャー関連事業に注力していましたが、さらなる営業効率の改善を狙いマーケティングオートメーション(MA)ツール導入に踏み切りました。特に、購入検討フェーズの見込み客を可視化し、競合の一歩先を行くサポート体制確立を目指しました。また、系列の別会社との共同作業も、マーケティングオートメーション(MA)ツールを共通の拠り所と位置付けることで、意識の擦り合わせがやりやすくなったようです。結果、新規顧客数や案件数も1.5倍の増加を記録しています。
その他にも、様々な業種業態におけるマーケティングオートメーション(MA)導入の成功事例を下記にてご紹介しておりますので、是非合わせてご一読ください。
9. まとめ
マーケティングオートメーション(MA)は便利な仕組みであり、企業の販売促進活動や生産性を向上することができる仕組みであることは間違いありません。ただ、マーケティングオートメーション(MA)と一言でいっても、「BtoB事業」と「BtoC事業」で大きく異なる点や、マーケティングオートメーション(MA)の前提はデータを活用することにあるため利用者にはデータやITリテラシーが求められる点など、詳細を理解せずに仕組みの構築やマーケティングオートメーション(MA)ツールの導入に取り組むと効果が出なかった、失敗した、という状態になりかねないので、マーケティングオートメーション(MA)の内容や具体をしっかりと理解して導入に取り組むことをおすすめします。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、マーケティングプロセス上に 存在する全てのビジネスデータを、ノーコードで、一元的に取得・統合・活用・分析することが可能なSaaS型データマーケティングプラットフォームであり、BtoC業界を中心に、様々な業種・業態のお客様にご導入頂いております。
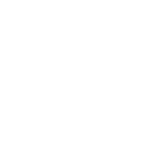
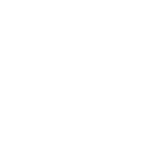

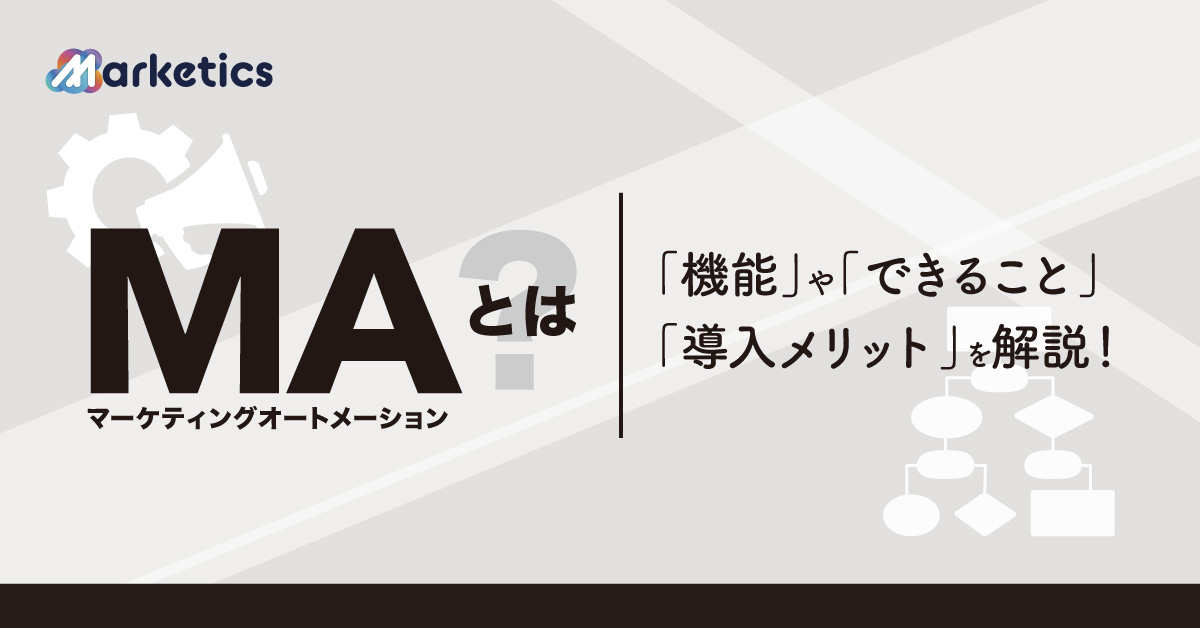
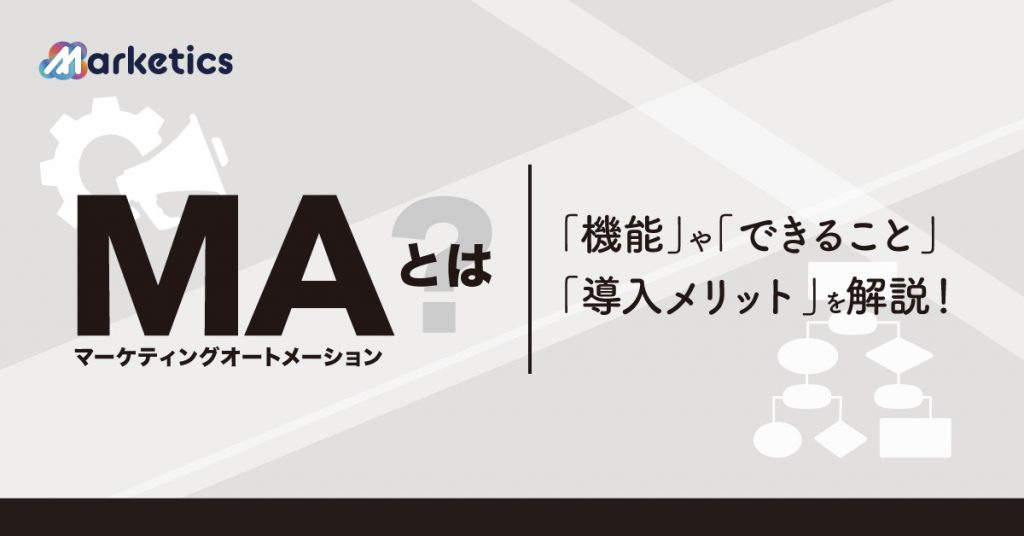
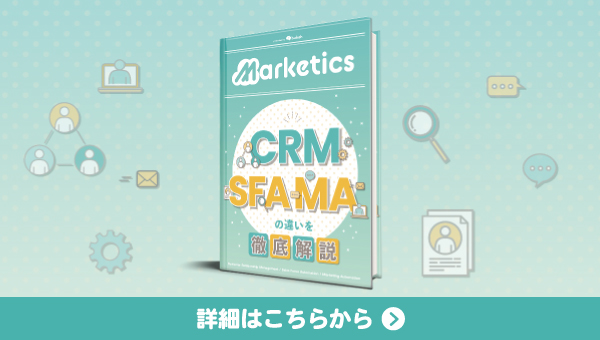

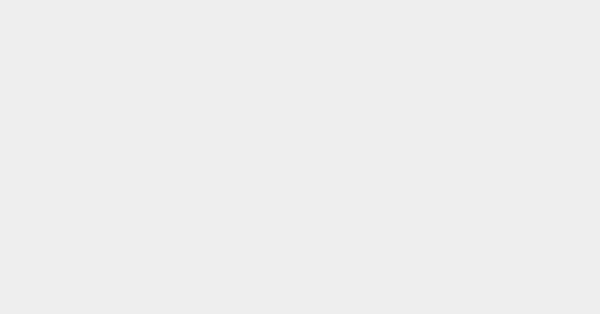
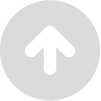
●目次
1. マーケティングオートメーション(MA)とは?
2. マーケティングオートメーション(MA)の主な機能
3. マーケティングオートメーション(MA)の効果は?
4. マーケティングオートメーション(MA)の市場規模
5. マーケティングオートメーション(MA)の目的
6. マーケティングオートメーション(MA)のメリット
7. マーケティングオートメーション(MA)導入時の注意点
8. マーケティングオートメーション(MA)導入の成功事例
9. まとめ