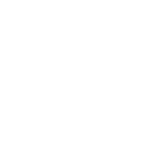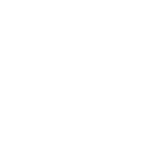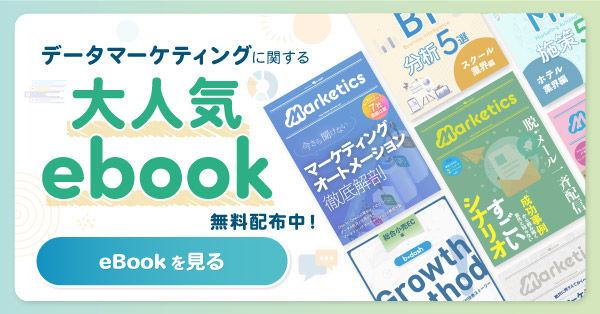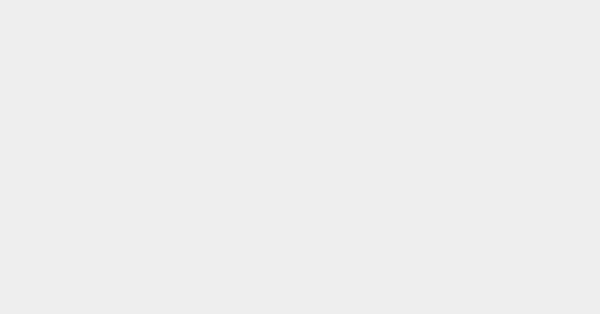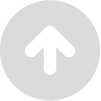今回はマーケティングオートメーション導入の前、つまりは前段部分の分析がとてつもなく重要であることをお伝えしたいと思います。中でも今回は、3C分析についてをピックアップします。
「ツールを入れればどうにかなるんじゃないか」と思われている方がいれば、今回は必ず読んでいただきたいです。
【参考】マーケティングオートメーションとは?
マーケティングオートメーション(MA)とは何か
〇なんでそんなに3C分析が必要なのか?
〇誰でもわかる3C分析
〇3Cでマーケティングオートメーションが変わる
なんでそんなに3C分析が必要なのか?
そもそもなぜ「3C分析が必要だ!」と訴えているのでしょうか?
料理に例えるとわかりやすいのですが、例えばカレーライスを作るときに、野菜・肉を切って、下ごしらえをしてからカレールーを入れ、鍋で煮込むと思います。
カレーを作るときに、下ごしらえなしでいきなり鍋にぶち込んでカレールーと一緒に煮込む人は流石にいないでしょう。そもそもそんなカレーは食べられる気がしません。
要は「下ごしらえ」
これが最も重要なのです。その「下ごしらえ」が3C分析なのです。
この3C分析をしっかりしないと、マーケティングオートメーション導入の失敗する可能性はかなり高くなるでしょう。この分析ではまず、分析をする前の仮説を構築します。
「自社のターゲット、訴求ポイントはここである」、「なのでマーケティングオートメーションではこのターゲットを狙う」このように、仮説を構築した後、分析に入っていきます。
では、次の章で3C分析の詳細をお伝えします。
誰でもわかる3C分析
最早使い古された感もある3C分析ですが、最も有名で使いやすいフレームワークだと思います。3Cは以下のように3つの分類に分かれます。
①顧客:Customer
②競合:Competitor
③自社:Company
①顧客:Customer
まずは顧客:Customerですが、これは市場も含みます。つまり、自社のいる市場、そして顧客の動向の分析を行っていきます。ここで注目していくのが「市場動向」、つまり変化です。市場規模の推移がどうなっているのか、将来予測、業界の市場だけでなく、商材の市場も調査する必要があります。
市場の変化を数値で捉えることが重要です。このように、まずは「定量データ」を集めます。次に、「なぜこの市場は伸びたのか?」
これを裏付けるためのトピックスを集めます。新商品が発売された、他業界の大手が参入してきたなど数値が伸びた、落ち込んだ要因を探します。
もちろんすべての要因は数字が伸びた時期や落ち込んだ時期とリンクしていなければなりません。これが市場の伸びの要因を探る「定性データ」です。
市場のデータと同じように、自社のターゲットとなる顧客のデータも定量・定性で収集します。収集したデータをまとめ、「市場はこのように変化している。変化する中で、チャンスはここにある!」
これを正確に出せるようにしましょう。数値上伸びている市場であり、ターゲットも豊富である。このような結論があればベストです。(そんな市場、今では珍しいですが、、、)
②競合:Competitor
次に競合:Competitorの分析を行います。競合他社と比較する際に気にするのは、「どのようなビジネスモデルで、どれくらい結果が出ているか、どこをターゲットとしているか」でしょう。
まずはビジネスモデル。
これはどのような収益構造になっているか理解する必要があります。
例えば、
売上はどうなっているのか?
顧客別、商品別、チャネル別でどのくらいの売上があるのか?
主要ターゲットはどこなのか?
主力商品はなんなのか?
どのチャネルで強いのか?
ヒアリングやWEB上での数値から算出ができますので、
そこから競合の市場シェアを導き出します。
上記から、このビジネスモデルの「強み」、「弱み」この2つをあぶりだします。これこそ競合とまともに戦うのか?というところの答えを出してくれます。
③自社:Company
最後に自社:Companyの分析です。
自社の分析では徹底的に自社の強みと弱みを各項目であぶりだします。
商品別、販促別、営業マン別(toBのみ)、チャネル別で自社のいったい何が強みなのかを導き出します。これら3分類から自社の強み、伸びている市場、商材、競合の弱み、すべて掛け合わせた答えを導き出します。
これを全て実施していよいよマーケティングオートメーション導入です。
3Cでマーケティングオートメーションが変わる
「マーケティングオートメーションを入れればどうにかなる」と思っていた方は、まず前段での分析が必要であるとご理解いただけたかと思います。
いきなりの導入は、基礎工事なしの建築、下ごしらえなしの料理です。
この分析をしっかりと行い、仮説の検証やマーケティングオートメーションの役割を定義していただければ、導入後の運用もうまくいく可能性は大幅に上がるでしょう。
導入前に改めて自社の強み、競合と比較して勝てるポイント、市場での機会を考えて、ターゲットを選択し、マーケティングオートメーションを導入しましょう。
【参考】マーケティングオートメーション導入に向けて
マーケティングオートメーション導入で注意すべき5つのポイント~導入で失敗する企業の特徴とは?~
<おすすめ記事はこちら>
● マーケティングオートメーション(MA) の概念を知りたい方
マーケティングオートメーション(MA)とは?
● マーケティングオートメーション(MA) のツールについて知りたい方
【2022年最新比較】おすすめMAツール10選+選び方
無料MA(マーケティングオートメーション)ツールおすすめ10選!
● マーケティングオートメーション(MA) の実践に関心がある方
MAのシナリオ設計のコツ!マーケティングで成果を生むには?
【厳選8事例】マーケティングオートメーション(MA) 導入の成功/失敗事例まとめ!効果は?
● マーケティングオートメーション(MA) の乗り換えを検討している方
MAツール乗り換えで失敗しないために抑えておくべきポイント4選

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、マーケティングプロセス上に 存在する全てのビジネスデータを、ノーコードで、一元的に取得・統合・活用・分析することが可能なSaaS型データマーケティングプラットフォームであり、BtoC業界を中心に、様々な業種・業態のお客様にご導入頂いております。
Editor Profile